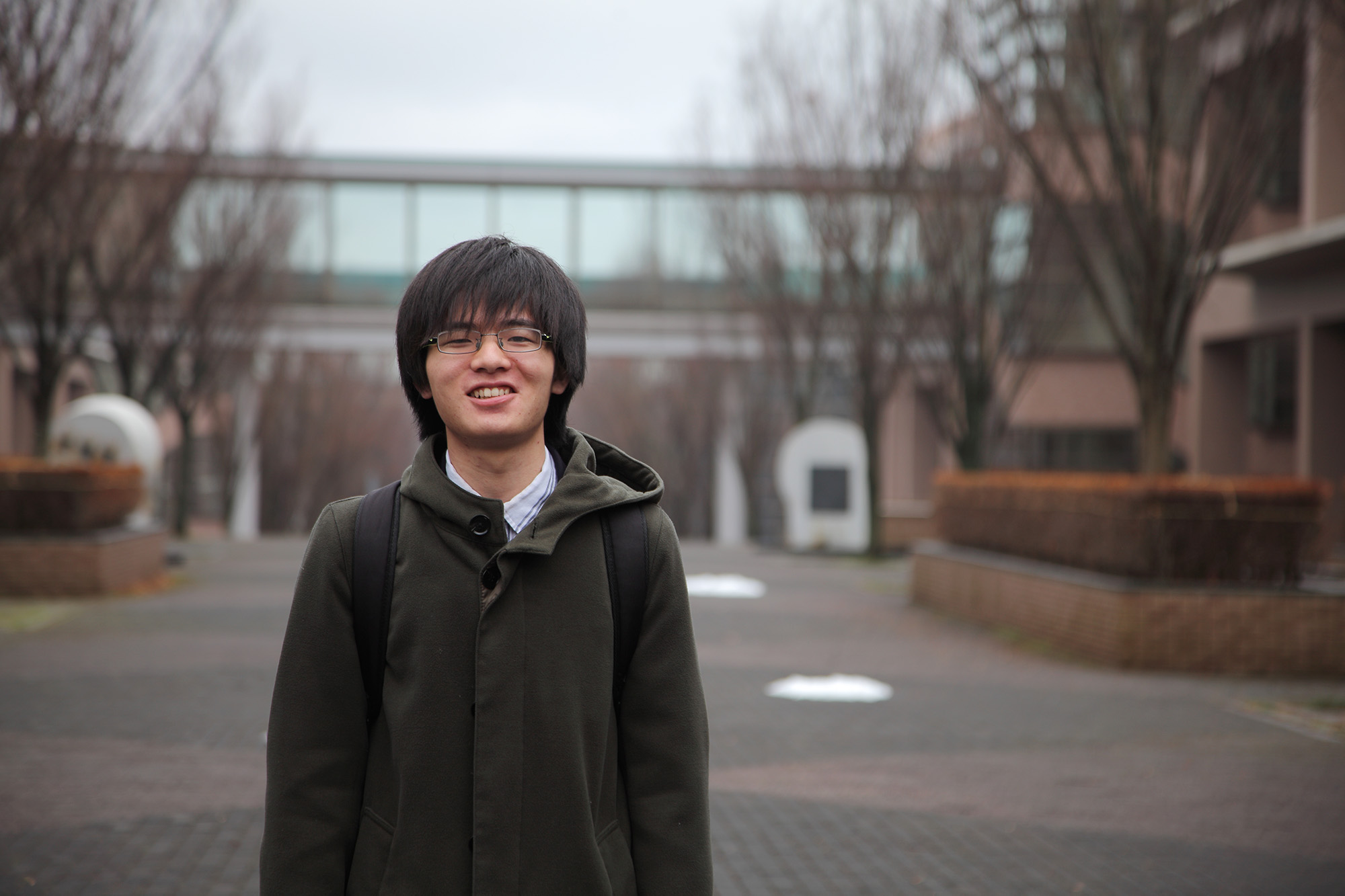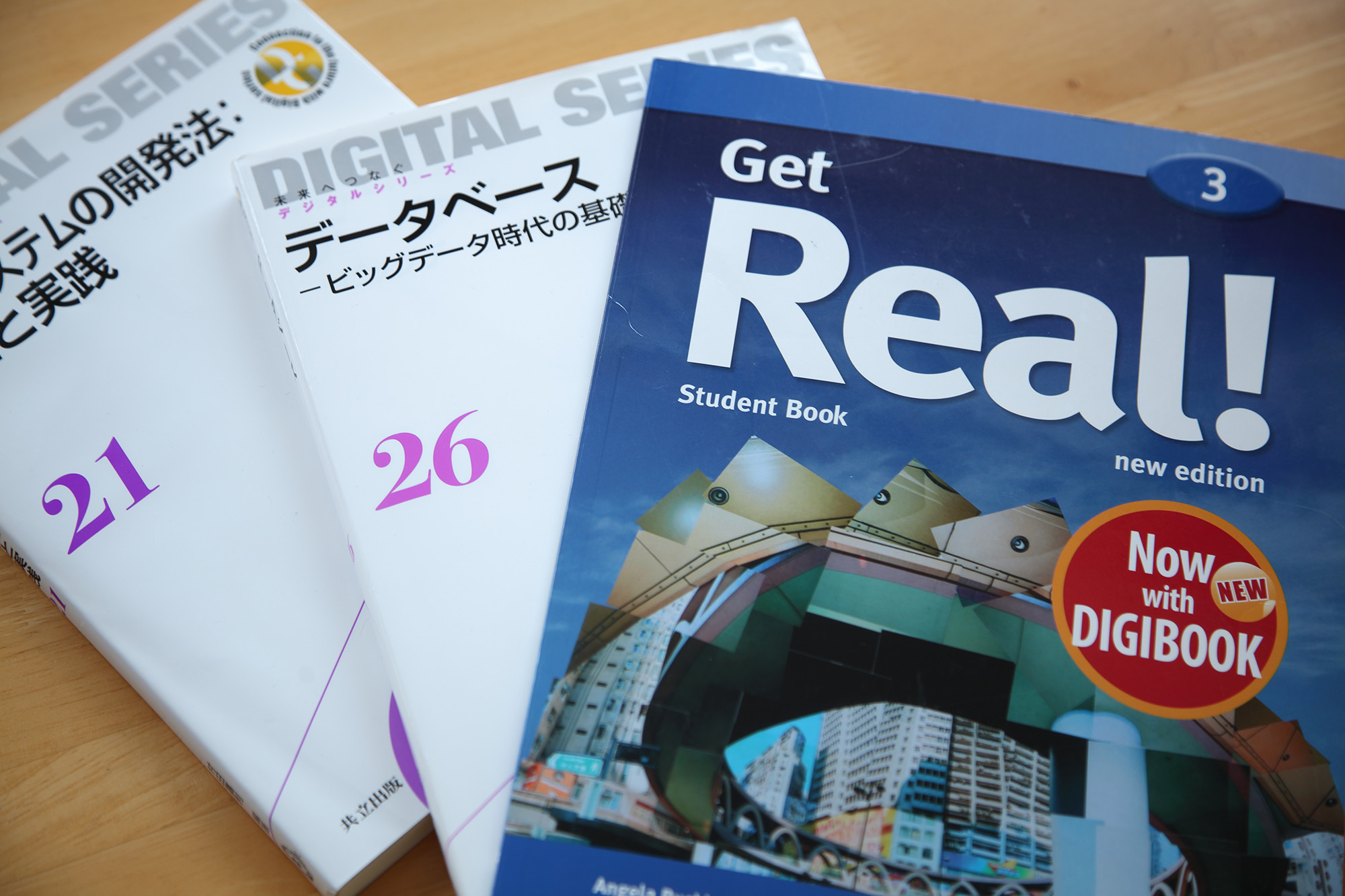第2期奨学生インタビュー第3回
AIで社会を豊かに ソフトウェア開発学ぶ
2017.12.23 (土)
日本財団夢の奨学金の2期生は、1期生と比べ、より広い範囲に散らばっています。インタビュー第3回は、東北で学ぶ岩手県立大学ソフトウェア情報学部2年、小笠原一樹さんです。
小笠原一樹、19歳。夢はソフトウェア開発技術者
11月下旬の祝日の朝、岩手県立大学の校内は、ひっそりとしていた。正門と思われる大きなアーチ型のモニュメントを見上げると、空は灰色。地面にはところどころ雪の塊がある。
「お待たせしました」
小笠原さんは、リュックサックを揺らしながら跳ねるようにやってきた。「数日前に雪が降って一面、積もっていたんですが、昨日は暖かかったのでずいぶん溶けました」。吐く息も白い。
「授業が休みの休日でも構いません。研究室は24時間いつでも開いてるんで」という小笠原さんの言葉に甘え、本格的な冬の到来の前にインタビューの日を設定したが、すでに東北は雪の季節になっていた。
キャンパスで笑顔を見せる小笠原さん。足元には雪が残っていた
小笠原さんがこのキャンパスで冬を迎えるのは2度目だ。「平均して一日2、3コマの授業があります。月曜日から木曜日までは朝の1、2限も入っていて、朝から夕方までびっしりと埋まっている日もありますね」。その他、週に1、2回ピザのデリバリーのアルバイトを入れ、月に1度ほどはフットサルのサークルで汗を流す。
2年生の現在、学ぶ領域はほとんどが専門のソフトウェアに関することだ。例えば、学部ならではの科目に「ソフトウェア演習A~D」がある。1年生前期から2年生後期にかけて、4つのステップで進む演習だ。プログラミング言語を学び、ホームページに必要な機能を個別に作ってみて、実際に作動するかなどの演習を行う。
「今は、データベースというパソコンのデータを保存する部分を、Java(ジャバ)と呼ばれるプログラミング言語を使って作っています」
プログラミング言語の学習は、ソフトウェア開発には欠かせないもの。この演習では、これまでにJavaのほかにもプログラミング言語を学んだ。しかし毎回、習得するのに大きな労力がかかるという。
「英語もプログラミング言語とは切り離せないのでやらなきゃいけない。もう大変です」。試験前は研究室に泊まり込んで、徹夜で勉強することも少なくないのだそうだ。
勉強に使うテキストには英語で書かれたものも含まれる
ただ、大変なことばかりではない。「プログラム言語は考え方や論理的思考が大事で、基本的な考え方は変わらないと分かってきました。プログラムができた時は、達成感もあります。うれしいです」
小笠原さんが他に「楽しい」と言って紹介してくれたのは、グループワークだ。実在する企業が抱えるシステム的な問題について理解し、その解決をグループで考えて競う授業では、5人前後のグループで作業した。「実社会の話なので、僕たち的には面白かったんです。物事を深掘りする作業が僕は好きで、それをみんなで取り組んだことが楽しかったですね」
ソフトウェア開発学部は、1学年に140人の学生がいる。機械やコンピューターを愛する人たちの集まりだ。「強い個性を持った人が多い」ため、すべての人とウマが合う訳ではないが、グループワークで達成感を共有したり、他大学と交流したりして、大学生活を楽しんでいる。
来年4月からは3年生になり、いよいよゼミに入る。「僕は、AI(人工知能)をやりたいと思います」。小笠原さんの頭には、すでに研究テーマが固まっていた。
「AIで、施設の子にももっと学びの機会を」
試験前には不夜城となる研究室で
夢の奨学金に応募した時、将来の夢は、「ソフトウェア開発のベンチャー企業の立ち上げ」だった。今も方向性は同じだが、1年経って、少し変化があったという。
「実際に起業した人など仕事をしている人たちに出会って、起業は簡単にはできないと分かりましたし、まずは社会に出て働いてみたいなと思うようになりました」
働くうえで小笠原さんが興味を持っているのが、研究テーマにも選ぼうとしているAIだ。関連書籍などを読んで、AIは「人とは何か」という哲学的なところがあることに気が付いたという。「人間味があるというか。そういうところが、面白い」と話す。
AIは昨今、よく耳にする言葉だ。だた、小笠原さんに言わせると、突然注目を集めるようになった領域ではないし、興味を持ったのも単に流行っているからではない。
「これまでにも大きな発見ごとにブームが来ていて、今回も 、ディープ・ラーニングという大発見があり、再びホットになっています。それに、AIが人間から奪ってしまう職業があると言われていますが、実際にAIが人になり替わって仕事をするのは、一部のルーティーン的な仕事を除いて、まだまだ先のことだと思います。あくまでも、機械は人の支援なんで」
そんな風にとらえている小笠原さんがAIに期待を寄せる理由は、この技術を応用すれば社会をより豊かにすることができると考えるからだ。「例えば、AIが勉強を教えるようになるとします。すると、ネット環境さえあれば児童養護施設の子にも、もっと学びの機会が出てくると思うんです」
リュックサックにはノートパソコンも。貸与のデスクトップと合わせてパソコンは2台使っている
幼いころから機械が好きだった。テレビゲームもやっていたが、授業でパソコンも触るようになった中学生ごろからは、「機械が人みたいになれば面白い。人じゃなければ、そこまで気を遣わなくてもいいから、なんだかいいな」とAIへの興味につながることを考え始めていた。
「小さい時に好きだったことを追いかけていたら、この道にたどり着いた」という感じだそうだ。フットサルを始めたのも、実は先にテレビゲームでやっていて面白かったから、と教えてくれた。
友だちと里親さんに恵まれて
小笠原さんが社会的養護の子になったのは、5、6歳の頃だ。岩手県内の児童養護施設に入り、高校2年生まで過ごした。理由は虐待だったと後年、伝え聞いたが自身ではあまり覚えていない。その後、進学準備などを理由に里親さんのところに移り、現在に至っている。来年には成人するが、大学卒業まで里親さんのところでお世話になる予定だ。
施設生活が長かったが、困難なことはあまり思い出にない。「施設は自分の居場所。だから、施設にいることに疑問を持つこともなく受け入れていましたし、普通の家庭の子どもと自分を区別することもあまりなかったです。学校の友だちも、自分の状況を詮索しませんでしたし、施設に遊びに来てくれることもありました。友人には恵まれてきたと思います」
施設を出て里親さんのところに行ったのは、ちょうど、高校で就職か進学かを考えていた頃だった。大学進学が選択肢に入ったことから、より静かな勉強の時間を得るために移った。里親さんの家では、個室を用意してくれていた。施設でも個室で勉強する環境はあったが、小さい子どもたちが遊びに誘いに来ると断れず、勉強に集中できなかったので、大きな変化になった。
里親さんについて語る小笠原さん
嬉しい変化はそれだけではなかった。
「安心感かな」。小笠原さんは、里親さんのところに行ってよかったことを尋ねられ、答えの一つとしてこう言った。「里親さんの家には現在、里親さん夫婦と成人したお嬢さん二人、そしてその一人の赤ちゃんと僕の全6人がいます。お嬢さんの一人が出産して赤ちゃんと一緒に滞在しているんです。赤ちゃんに癒されています」。説明する小笠原さんの表情も明るい。
「普通のことかもしれませんが、みんなで食卓を囲む時、安心します」。全員がテーブルにつき、「いただきます」と言って食事が始まる。目の前には温かいおいしい料理。家庭の経験がなかった小笠原さんにとって、その一場面は心を動かされるものだった。「あったかい空間、とでもいうんですかね」
「棚までは自分で走る」の言葉に一念発起
夢の奨学金の情報も、この里親さんからもたらされた。
小笠原さんにとって自立に向けての課題は、住むところと、お金のこと。大学進学にあたって、住まいは里親さんにお世話になることになったが、お金のことは奨学金に頼ることになった。この時、里親さんが丹念に調べてくれたおかげで奨学金を得ることができ、無事に入学することもできた。
ただ、入学できても、日々の生活や学業にはお金がかかる。この先どうなるか不透明な状況が続いていた中、里親さんが「こんな奨学金があるらしいよ」と小笠原さんに語ったのが、夢の奨学金だった。
研究室のある4階フロア。祝日の早朝にもかかわらずパソコンに向かう学生さんがいた
学費が全額出るだけでなく、生活費も出る。しかも、返済の必要はない。条件を聞いて、小笠原さんは「きっと自分なんかは受からない」と思ったが、里親さんのある一言で、応募を決意した。
「『棚から牡丹餅』という言葉があるけど、棚まで自分で走らなきゃお餅は手にできないんだよ、とおじさん(里親さん)から言われました。運にも恵まれることが必要だけれど、それには努力も必要なんですよね。じゃあやってみるか、と思いました」
里親さんからはこれまで、様々なサポートをしてもらっていた。部屋の掃除、服装、時間厳守…。社会人としてのマナーも含めて、日常の様々なことを細かに教えてくれていたが、夢の奨学金の応募でも、里親さんは強力な助っ人になってくれた。
応募書類の文章については、里親さん自身が添削をしてくれた。面接に向けては、知人の大学教授にお願いしてくれ、小笠原さんはその人と模擬面接を繰り返した。「ここまでやられたら、受かるしかないという気になりました」
結果は合格。信じられなさと安堵で、呆然としている小笠原さんの肩を、里親さんはポンとたたいて「一生分の運を使い果したんじゃないか」と笑顔だったという。
夢の奨学金をもらえるようになって、「心に余裕ができた」と小笠原さんは話す。「社会に出た時に借金がたくさんあると大変だという危機感があったんです。何とかやりくりして借金を作らないで済むように頑張っていましたが、この奨学金に合格したことは、将来の希望につながりました」
サポートしてくれている人への感謝の気持ちと、危機感からの解放が、小笠原さんの学ぶ意欲をより大きなものにしている。
大学生活も、間もなく折り返し地点にさしかかる
社会的養護の後輩、申請を予定している人へのメッセージ
「進路を決めるには、自分の気持ちが大事。世間体や親などではなく、自分の気持ちを第一にして、何がやりたいのか、その他に何をすればいいのかを考えてみてほしい」
「スティーブ・ジョブズの言葉に、『人生は点と線だ』と言うのがある。経験は点に過ぎないけれど、それを重ねていけば、点がいつか繋がっていく。過去を振り返ったり、未来を考えたりするのもいいけれど、今していることを精いっぱいやってほしいと思います」